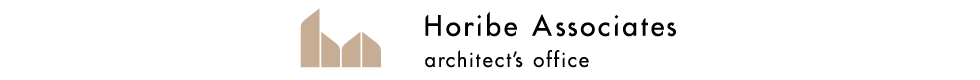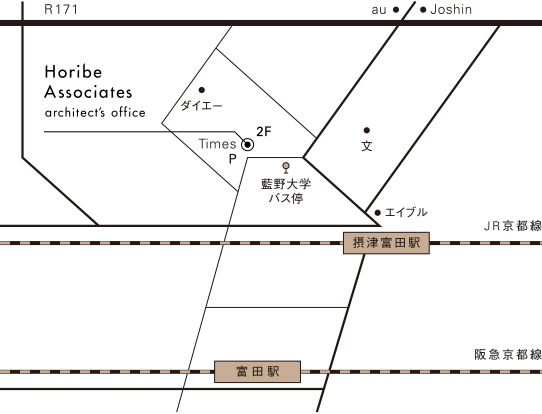blog
マンション改修工事/現地説明会/東京都江戸川区
2024.06.14 / Horibe Associates
東京都江戸川区で計画を進めているマンションの改修工事
現地での説明会を行いました。

見積りに参加いただく施工会社様に現地にお越しいただき、主に外装や共用部について改修内容の確認を行いました。
竣工後35年以上大きな改修工事を行ってこられなかったことと、一部建具周りに最近施工されたコーキングの後が見受けられましたが、既存シールの上への増し打ちだったため、コーキングの必要断面も確保されず本来の性能を満たしていないことなどから、コーキングや屋根の防水の刷新を主体工事とし、現在空室となっている1室については内部のリノベーションも行うことになりました。

(経年劣化した外壁コーキング)
築35年となると外壁のコーキングは紫外線の影響を受けやすい部分は特に劣化が激しく、表面もひび割れており、弾力性も全く無くなっていました。
こうなるとALCパネルの挙動への追従性もなく、止水性能も著しく低下しているため早急な工事が必要となります。
8月の工事着手を目標に、図面作成、見積り依頼、金融機関との融資調整等々慌ただしくなってきました。
【NEWS】
2024/5/9 14年間の改良を重ねてtoolboxさんとの共同開発「天井スリットファン」が発売されました。
2023/8/12 初の著書「建築設計のデジタル道具箱」が学芸出版社より出版されました。
ジャズストとポンポン山トレイル
2024.06.11 / Horibe Associates
早くも先月のことになりますが、毎年仕事関連のイベント事が多く、なかなか参加できていなかった高槻ジャズストリートへ今年は行くことができました。
しかも欲張って午前中は友人、愛犬と一緒にポンポン山登山も敢行。
昨年真夏に登ったときとは違って気持ちの良い気候でした。

樹齢数百年の古木「天狗杉」で休憩

まだ2歳の元気なエルマーも頂上まで抱っこ無しで駆け抜け、2度目の登頂に成功しました。
下山しそのままジャズスト会場へ
ジャズストでは野見神社さんで音楽を聴きつつ、竣工したばかりのCafe N+の様子もチェック。
友人にオススメしてもらった「Shiho with 桑原あい」のステージも最高でした。
堀部直子
【NEWS】
2024/5/9 14年間の改良を重ねてtoolboxさんとの共同開発「天井スリットファン」が発売されました。
2023/8/12 初の著書「建築設計のデジタル道具箱」が学芸出版社より出版されました。
ガレージハウス/植栽打合せ/兵庫県宝塚市
2024.06.04 / Horibe Associates
宝塚で計画中のガレージハウス 植栽工事の打合せを行いました。

作庭は和想デザインさん
今回は和想さんの担当の方に現場に来ていただいての打合せ。

到着したのはランチア・フルヴィア 1963年から76年まで製造・販売されたイタリア車 約50年前の車です。
ジュリア・スプリント・ベローチェにも似た顔がキュート。
いつものことですが、打合せが始まる前に車の話題でなかなか本題に入れません
さて、植栽のほうは現場の掘削工事で出てきた石を「景石」に使用し、シンボルツリーは「白く小さな花の咲く木」というオーダーで。

ガレージからつながる中庭は浴室やキッチン、リビング、2階テラスにも面していて、生活シーンの様々な場所からシンボルツリーが見え隠れし、生活に彩りを与えてくれます。
【NEWS】
2024/5/9 14年間の改良を重ねてtoolboxさんとの共同開発「天井スリットファン」が発売されました。
2023/8/12 初の著書「建築設計のデジタル道具箱」が学芸出版社より出版されました。
【公式SNS】
建築家の日常を綴るインスタグラムの新しいアカウントを開始しました。
@horibeassociates_daily←follow me!
@horibeassociates(Official Instagram)
Facebook
竣工写真/神社カフェ/大阪府高槻市野見神社
2024.06.01 / Horibe Associates
大阪府高槻市の野見神社で計画していたカフェ 「Cafe N+」が完成し竣工写真の撮影を行いました。
撮影は三木夕渚氏。
三木さんには、このプロジェクトが始まった頃から構想のイメージについてや、実施設計の前にイタリアはヴェローナのカステルヴェッキオ美術館の視察をしておきたいといったこと、その旅で観ておくべき建築など様々相談させていただいていました。
ですので撮影当日現地では特に細かな説明もなく撮影はスタート
「夕景は天気の良い明日へ」ということで2日間に渡る撮影が終わりました。
こちらはお気に入りの一枚

コンセプトに通じる周辺環境やその文脈を的確にフレームに納めつつ、建築を中心に据えプロポーションは美しい絵画のようです。
こうあるべきと考えた「建築の建ち方」を、最も相応しい構図で捉えていただきました。


高槻城と野見神社 この建築が土地の記憶を継承し、末長く地域の顔として愛される建築でありますように。
Cafe N+(カフェ エヌ プラス)
設計監理:Horibe Associates
構造設計:高橋俊也構造建築研究所
施工 :小阪工務店
木工事 :巧技工務店
写真 :三木 夕渚
【NEWS】
2024/5/9 14年間の改良を重ねてtoolboxさんとの共同開発「天井スリットファン」が発売されました。
2023/8/12 初の著書「建築設計のデジタル道具箱」が学芸出版社より出版されました。
【公式SNS】
建築家の日常を綴るインスタグラムの新しいアカウントを開始しました。
@horibeassociates_daily←follow me!
@horibeassociates(Official Instagram)
Facebook
ガレージハウス/家具工事着手/兵庫県宝塚市
2024.05.28 / Horibe Associates
宝塚で計画中のガレージハウス 家具工事が始まりました。


施工図で何度も調整を行い、工場で仮組みされたものが現場へ搬入され設置されます。
家具工事は何度もご一緒させていただいた家具屋さんで図面では表現しきれないような部分も的確に確認していただき、施工に落とし込んでいただけます。
家具や建具は毎日目にして、手に触れる生活の中でもっとも近い存在です。
利便性と強さと美しいディテール。用強美が共存しなければいけないものですので、信頼できる造り手の方に対応いただけて今回も安心です。
【NEWS】
2024/5/9 14年間の改良を重ねてtoolboxさんとの共同開発「天井スリットファン」が発売されました。
2023/8/12 初の著書「建築設計のデジタル道具箱」が学芸出版社より出版されました。
【公式SNS】
建築家の日常を綴るインスタグラムの新しいアカウントを開始しました。
@horibeassociates_daily←follow me!
@horibeassociates(Official Instagram)
Facebook
地鎮祭/民泊・ワーケーション施設/大阪府阪南市
2024.05.24 / Horibe Associates
阪南市で計画中の民泊施設 地鎮祭を行いました。

高台に位置する敷地からさらにRC駆体でレベルを上げ、リビングダイニング、浴室、サウナなど様々な場所から海や街の夜景を楽しみながら過ごすことのできる空間。


確認申請の作業も終盤を迎え、施工計画等の準備に入りました。

写真は神酒拝戴(しんしゅはいたい)の際に配られた盃。梅の花のように配置されていました。
地鎮祭を執り行っていただいた宮司さんは、事前の手ほどきから、豆知識までとにかく親切、丁寧でお話しもとても面白く、明るく笑いの絶えない地鎮祭となりました。
【NEWS】
2024/5/9 14年間の改良を重ねてtoolboxさんとの共同開発「天井スリットファン」が発売されました。
2023/8/12 初の著書「建築設計のデジタル道具箱」が学芸出版社より出版されました。
【公式SNS】
建築家の日常を綴るインスタグラムの新しいアカウントを開始しました。
@horibeassociates_daily←follow me!
@horibeassociates(Official Instagram)
Facebook
完成見学会/神社カフェ/大阪府高槻市野見神社
2024.05.20 / Horibe Associates
大阪府高槻市の野見神社で計画していたカフェ 「Cafe N+(カフェ エヌ プラス)」が完成しプレオープンの際に完成見学会を開催させていただきました。

全ての工事が完了したのは前日の夕方、最短納期3ヶ月で入荷日がギリギリまでわからなかったFLOSの照明器具も前日に到着。

植栽工事も完了し残工事無しでオープンを迎えることができました。
現場監督さん始め全ての職人さんが少しでも良いものを残そうと前向きに対応していただき、オープンまでの差し迫った状況でも施工図での検討や改善案の提案など、気が利いて本当に協力的で
竣工間際にいろいろ出てくる追加や変更も皆全力で取り組んでいただき満足いく形で終えることができました。
優秀なメンバーが揃い本当に素晴らしいチームでした。

(犬用水飲み場の鍵付き水栓 RC壁のモックアップで作成したコンクリートの塊に手書きで描いたサイン)

(既製品のドアストッパー以外で・・・と考えた流木や自然石で対応できるドアストッパー)
ゴールデンウィーク前半の2日間で開催した見学会はたった18m2の小さな建築に107名もの方々に、神戸・京都・奈良・遠くは加古川からもお越しいただき大盛況でした。
お越しいただきました皆様ありがとうございました。
関係者の皆さま、そしてクライアントにこの場をお借りしてお礼申し上げます。
Cafe N+(カフェ エヌ プラス)
設計監理:Horibe Associates
構造設計:高橋俊也構造建築研究所
施工 :小阪工務店
木工事 :巧技工務店
【NEWS】
2024/5/9 14年間の改良を重ねてtoolboxさんとの共同開発「天井スリットファン」が発売されました。
2023/8/12 初の著書「建築設計のデジタル道具箱」が学芸出版社より出版されました。
ガレージハウス/塗装工事確認/兵庫県宝塚市
2024.04.29 / Horibe Associates
宝塚のガレージハウスは造作工事が間もなく完了します。
これから塗装工事、内装工事、家具工事と進んでいき、いよいよ竣工へ近づいてきました。

こちらは基礎の納まりで壁の厚みが変わるためデザインした棚。写真と説明ではわかりにくいと思いますので、詳細は内覧会で。
階段上の天井を高さ確保のために斜めに納めた床端部の詳細。
先端のRの木は節が少なく品のある木目が特徴のアガチスを採用しました。

【床単部の詳細写真】

【BIMモデル】
BIMモデルで自由気ままに検討した造作のディテールを完全に再現していただいた凄腕大工さんの仕事です。
次の吹田の家も担当していただけるとのことで安心です。
【NEWS】
2024/4/10 メタバース総研にてBIM・VRの取組みを紹介していただきました。
2024/3/7 公式LINEアカウント開始しました。
2023/10/1 建築ジャーナル10月号に7作品掲載されました。←NEW!
2023/8/12 初の著書「建築設計のデジタル道具箱」が学芸出版社より出版されました。
地鎮祭/三角形の敷地の家/大阪府吹田市
2024.04.27 / Horibe Associates
大阪府吹田市で計画中の「三角形の敷地の家」
地鎮祭を行いました。

今回はクライアントに事前に神社でお参りいただき、現場では施主設計施工の3者で行う簡易な地鎮の儀を執り行いました。
事前にお参りいただいたのは、移転や転居といえば「ほうちがいさん」と言われる堺市の方違神社

古来から方災除けの神様として知られ、方位の災いから身を守り「吉方」へ導かれると言い伝えられ、新築・転居等の厄除けで全国からたくさんの人々が参詣に来られる神社です。
地盤改良計画書、プレカット図、鉄骨階段製作図等 品質書類や施工図のチェックに早速追われています。
長期優良住宅の申請が完了すればいよいよ着工です。
【NEWS】
2024/4/10 メタバース総研にてBIM・VRの取組みを紹介していただきました。
2024/3/7 公式LINEアカウント開始しました。
2023/10/1 建築ジャーナル10月号に7作品掲載されました。←NEW!
2023/8/12 初の著書「建築設計のデジタル道具箱」が学芸出版社より出版されました。
【公式SNS】
建築家の日常を綴るインスタグラムの新しいアカウントを開始しました。
@horibeassociates_daily←follow me!
@horibeassociates(Official Instagram)
Facebook
大阪府公共建築設計コンクールのプレゼンテーション会へ出席
2024.04.25 / Horibe Associates
「あすなろ夢建築」大阪府公共建築設計コンクールのプレゼンテーション会へ出席してきました。

審査会結果は先月報道発表されていますので、受賞者のみのプレゼンテーションです。
これによって順位が変わることはありませんが、学生の皆さんが改めて設計のコンセプトや提案内容を大勢の人の前で発表でき、私たち審査委員および審査委員長の質疑にもその場で答えるなど、今後の設計活動においてとても良い経験になる場だと感じました。

学生さんたちは引率の先生方に見守られているからか、少し緊張はしているようでしたが、物怖じしない学生らしい受け答えで、私たちの指摘やアドバイスも熱心に聞いてくれていましたが、むしろ設計指導をされていた先生方の心配そうな面持ちが印象的でした。
また先日鈴木毅先生の最終講義を聴講に行った際に、私の大学時代の恩師である小島孜先生から、この「あすなろ夢建築」は小島先生や鈴木先生が大阪府に「若者に夢とチャンスを!」と呼びかけて、30年以上前にスタートしたコンクールであることを知りました。
偶然とはいえ、恩師の思いでスタートしたコンクールのお手伝いができたことは、とても嬉しく感じました。
堀部直子
【NEWS】
2024/4/10 メタバース総研にてBIM・VRの取組みを紹介していただきました。
2024/3/7 公式LINEアカウント開始しました。
2023/10/1 建築ジャーナル10月号に7作品掲載されました。←NEW!
2023/8/12 初の著書「建築設計のデジタル道具箱」が学芸出版社より出版されました。
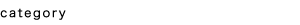
-
- ARBOLEDA LP884 (13)
- D社新社屋 (1)
- Mountain Sea Villa (7)
- たつのギャラリー (22)
- つくばの家 (4)
- はつが野の家 (11)
- イロイロ (162)
- オーナーズボイス (8)
- オープンハウス案内 (13)
- ギャラリーあしやシューレ (6)
- グルメ (1)
- テニスクラブ (3)
- マンションリノベーション (18)
- 三好の家 (8)
- 三田の家 (14)
- 三田市の平屋 (4)
- 上八万の家 (6)
- 下河東の家 (16)
- 世田谷アパートメント (40)
- 丸亀の家 (9)
- 交野の家 (3)
- 交野の診療所 (3)
- 京終の家 (3)
- 伏石の家 (6)
- 十月桜の家 (4)
- 千里山の家 (5)
- 名神町賃貸PJ (8)
- 吹田の家 (10)
- 吹田松が丘の家 (4)
- 和歌山市の二世帯住宅 (5)
- 塚脇の家 (17)
- 宇佐のドッグサロン (9)
- 安満磐手の長屋 (5)
- 宝塚のガレージハウス (13)
- 山坂の家 (17)
- 山城の家 (1)
- 山川の家 (7)
- 岬町の家 (2)
- 川越の家 (19)
- 平野の家 (3)
- 戸建てリノベーション (8)
- 摩湯の家 (5)
- 旭ケ丘の家 (10)
- 昭和台の家 (2)
- 本町の家 (1)
- 杉江の家 (23)
- 東上牧の家 (7)
- 東上牧の家2 (5)
- 東住吉の家 (15)
- 東谷の家 (5)
- 浜寺の家 (1)
- 深井の家 (20)
- 瀬戸の家 (2)
- 熊取の家 (26)
- 熊本の家 (17)
- 白ばら英会話学校 (92)
- 目黒区の賃貸併用住宅 (2)
- 真上の家 (17)
- 私市の家 (22)
- 紀の川の家 (10)
- 藍畑の家 (5)
- 藤井寺の家 (1)
- 認定こども園 (1)
- 野見神社CAFE (17)
- 青谷の家 (11)
- 飲食店舗 (4)
- 香里ヶ丘の家 (16)
- 高山台の家 (5)
- 高山台の家2 (11)
- 鳴門の家 (7)
- 鴨島の家 (2)
- Y社新社屋 (3)
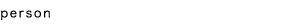
-
- Horibe Associates (845)
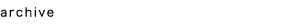
-
- 2024-07 (6)
- 2024-06 (8)
- 2024-05 (3)
- 2024-04 (14)
- 2024-03 (15)
- 2024-02 (13)
- 2024-01 (2)
- 2023-11 (1)
- 2023-10 (1)
- 2023-09 (1)
- 2023-06 (2)
- 2023-05 (2)
- 2023-01 (2)
- 2022-09 (2)
- 2022-08 (1)
- 2022-05 (1)
- 2022-04 (8)
- 2022-03 (1)
- 2022-02 (1)
- 2021-10 (1)
- 2021-07 (1)
- 2021-05 (1)
- 2021-03 (1)
- 2021-02 (4)
- 2021-01 (3)
- 2020-10 (2)
- 2020-09 (13)
- 2020-08 (2)
- 2020-07 (3)
- 2020-05 (3)
- 2020-04 (1)
- 2020-03 (8)
- 2020-01 (2)
- 2019-12 (1)
- 2019-11 (2)
- 2019-09 (1)
- 2019-08 (1)
- 2019-07 (9)
- 2019-06 (1)
- 2019-05 (2)
- 2019-04 (4)
- 2019-03 (1)
- 2019-02 (3)
- 2019-01 (5)
- 2018-12 (2)
- 2018-11 (3)
- 2018-10 (3)
- 2018-07 (4)
- 2018-06 (9)
- 2018-05 (9)
- 2018-04 (4)
- 2018-03 (1)
- 2018-02 (6)
- 2018-01 (14)
- 2017-12 (2)
- 2017-11 (1)
- 2017-10 (8)
- 2017-09 (7)
- 2017-07 (13)
- 2017-06 (10)
- 2017-05 (2)
- 2017-04 (6)
- 2017-03 (17)
- 2017-02 (9)
- 2017-01 (1)
- 2016-12 (7)
- 2016-11 (5)
- 2016-10 (3)
- 2016-09 (10)
- 2016-08 (8)
- 2016-07 (5)
- 2016-06 (7)
- 2016-05 (11)
- 2016-04 (4)
- 2016-03 (7)
- 2016-02 (12)
- 2016-01 (9)
- 2015-12 (9)
- 2015-11 (13)
- 2015-10 (11)
- 2015-09 (5)
- 2015-08 (13)
- 2015-07 (15)
- 2015-06 (10)
- 2015-05 (8)
- 2015-02 (6)
- 2015-01 (8)
- 2014-12 (4)
- 2014-11 (2)
- 2014-10 (12)
- 2014-09 (13)
- 2014-08 (12)
- 2014-07 (8)
- 2014-06 (15)
- 2014-05 (20)
- 2014-04 (17)
- 2014-03 (22)
- 2014-02 (22)
- 2014-01 (18)
- 2013-12 (13)
- 2013-11 (17)
- 2013-10 (22)
- 2013-09 (23)
- 2013-08 (26)
- 2013-07 (16)
- 2013-06 (11)
- 2013-05 (9)
- 2013-04 (2)
- 2013-03 (1)
- 2013-02 (1)
- 2013-01 (1)
- 2012-11 (1)
- 2012-10 (1)
- 2012-09 (1)
- 2012-08 (1)
- 2012-07 (1)
- 2012-06 (5)
- 2012-05 (3)
- 2012-04 (3)
- 2012-03 (2)
- 2012-02 (4)
- 2012-01 (4)
- 2011-12 (2)
- 2011-11 (2)
- 2011-10 (2)
- 2011-09 (1)
- 2011-08 (2)
- 2011-07 (5)
- 2011-06 (5)
- 2011-05 (3)
- 2011-04 (2)
- 2011-03 (3)
- 2011-02 (3)
- 2011-01 (4)
- 2009-01 (1)
- 2008-10 (1)
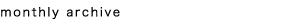
-
- 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12